2XXX年Y月Z日。人工島『オリオン』。
二人の男女が空を見上げていた。空には満月が浮かんでいた。
「いよいよ明日ね」
「ああ、そうだな」
月を見ながら呟いた女の言葉に男が応えた。
「あれからもう3年か」
南南西から微風が吹いていた。明日の天気は快晴。この分なら何も問題はない。明日はその月へと向かう。
3年前に突如として、宙を覆いつくした宇宙嵐の影響で磁場が乱れ、地球にかなりの被害が出た。衛星との通信が途絶し、GPS(全地球測位システム)が機能しなくなった。それに頼っていた都市機能は完全にマヒした。
定期的に行き来していた地球と月の往来が出来なくなっていた。加えて一切の通信機器も使えなくなり音信不通となった。人類は宇宙嵐が過ぎるのを待つしかなかった。
宇宙嵐が過ぎ去り、通信障害は回復したはずであったが、相変わらず月への連絡が取れなくなっていた。この状況を由々しき事案として宇宙連邦協議会(SFC)は月へ偵察部隊を出すことになった。
このことを社内報で知ったミライは、真っ先に統括であるセシルの席に駆け寄った。
「お願いだから、セシル。私に行かせてくれ」
ミライは腹部かと頭を下げた。その光景に一同が振り向いた。
「そういや、ミライの弟が月にいるんだったな」「気持ちは分かるが、もう全滅してるんじゃ・・・」と周りからヒソヒソ話が聞こえる。この3年の間にミライはそんな言葉は何度も耳にしていた。もう慣れていた。
「おい、誰だ?滅多なことを言うもんじゃない」
セシルが皆を制した。
「ミライ、頭をあげろ。そんなことしたってムダだ。メンバーは総合的に判断して公平に決める。私情は挟まない」
「まあ、そう言うなよ」
そこへ同僚のアシタが割り込み、
「ミライは優秀な宇宙飛行士だ。客観的に見てもミライなら申し分ないだろ。おれからも頼む」
ミライの隣で土下座した。
セシルは大きなため息を付いた後、
「だったらアシタ、客観的に見て、おまえ以上の経験のあるパイロットもいない。月へ一緒に行ってくるんだな」
こうして翌日には月に行くメンバーはミライ、アシタを含む10名が選考された。
今から3年と少し前・・・。
ミライとシンセは二人で暮らしをしていた。幼いころに両親を亡くし、他に身寄りも無く、ミライがシンセを育ててきた。
「受かったの?あの試験に?」
ミライは思わず身を乗り出した。
「うん」
夕食のシチューを頬張りながら、シンセはうなずく。
「うんってあんた、世界中から応募があって競争倍率1万倍って聞いてるわよ」
「それは盛ってるって。正確には8251倍だよ」
シンセはジャガイモにかぶりつく。
温暖化、洪水、干ばつ、大気汚染、海面上昇など地球環境の悪化は年々進んでおり、その間にいくつもの国が消滅した。
月への移住は人類の長年の夢だった。月面基地が完成して6年の月日が経過していた。次なるステップとして人が長期的に滞在するための施設も作られた。
条件は15~25歳までの若い男女であること。人種は問わない。1次の知能テストから始まり、2次の体力テスト、3次の面接テストを突破した120名が選抜された。
「あんたたちは人類の希望なんだから頑張っておいで」
「ああ、行ってくる。姉ちゃんも元気でね」
シンセは空っぽになった皿を差し出した。
「そんなことよりおかわり頂戴」
しばらくして訓練施設に入るためにシンセは16年間暮らしてきた家を出た。ミライはそれっきり弟とは会っていない。
「あと5分で最終フェイズに入ります」
管制室にミライの声が届くとにわかに騒がしくなった。月に行く宇宙船は発射準備に入っていた。3年前までは月に行く定期便が週に一度はここから往来していた。3年ぶりの運用ということもあって誰もが緊張していた。
宇宙船は発射台へと移動されて誘導灯が点灯する。着座したままのミライたちがエンジンへの点火を待っていた。その臨界温度は千度を超える。冷却装置がフル稼働を始めた。
「ん・・・?」
最初にそれに気付いたのは管制室へ配属されたばかりのアーサだった。
「レーダーに反応。この空域に何かが接近してきます」
モニターが切り替わり、アラートとともに高速で移動する赤い点が表示されていた。
「この空域には立ち入り制限が出ているだろう。どこのバカだ?」
セシルは眉をひそめる。
「こ、これは、航空機にしては速過ぎる・・・。あと600秒でここに到達します」
管制室がどよめきが起こった。
「まさかミサイルか?どこの国からだ?」
セシルは語気を強めた。
アーサは頭がパニックになりそうだった。理性を保つのに精一杯だった。ミサイルなんて学校で習っていない・・・。
「いえ、これはミサイルではありません。この軌道は宇宙からです」
管制室のモニターが切り替わり、空から落ちてくる光球が写し出された。
「なんだと。隕石か?」
額から吹き出す汗が止まらないアーサは目の前にある数値から答えを導き出した。
「こ、これ、ここに直撃します。皆さん、今すぐに退避してください!!」
「もう間に合わん。宇宙船の発射は一時中止。全員衝撃に備えろ」
セシルが言い終えると同時にガタガタと机の物が揺れ始めた。次の瞬間には凄まじい轟音とともに突き上げるように建物全体が揺れた。管制塔の全モニターがブラックアウトした。
人工島を支える柱はフロート式で海上に浮いており、海面から30m以上の高さがある。そのため揺れにくい構造になっているが、その人工島が揺れた。打ち上げられた海水が雨のように降り注いでいた。
「全員無事か?」
暗がりの中でセシルは立ち上がり、周りに呼びかけた。非常灯のわずかな灯りが床に四散した物を照らしていた。
「電源回復します」
管制室の電灯、全モニターが復旧し、島中に設置されたカメラ映像が映し出された。
セシルはその一部に目を止めた。モニターを指差し「拡大しろ」と指示した。
「隕石じゃなかったのか」
そこには着水したそれが映し出されていた。
海面に浮かび、ゆっくりと旋回して人工島へ向かってくる。その形には見覚えがあった。それは打ち上げようとしていた宇宙船と同じ形状をしていた。
海面から出た上部のハッチが開き、中から人が出てきた。若い男のようだった。装着していたゴーグルを外し大きく手を振った。
「何か喋ってる。マイクで拾えるか?」
アーサが頷いて、パネルを操作する。若い男の声が徐々に声が鮮明になってくる。
「・・・た・・い・・・て・、ただいま」
その様子は宇宙船のコックピットのモニターにも映し出されていた。先ほどの衝撃で発射台が傾き、宇宙船もコックピットも大きく傾いていた。ここは無重力でも物が散らばらないように固定されてある。
「シンセ!?」
ミライはその若い男の姿に見覚えがあった。ミライはモニターにかぶりついた。
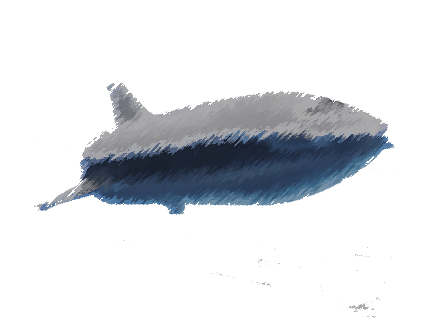
海から引き揚げられた宇宙船を大勢の人間がザワザワと取り囲んでいた。
「改造されてる・・・。こいつはすごい」
「あんなスピードで曲がれるのか」
人工島と衝突しそうになったが、衝突の寸前で急に軌道を変えて水切りのように海面を何度か跳ねて着水した。
シンセは人だかりのその中心にいた。XRゴーグルから周囲に映像が投影されて説明を繰り返す。矢のような質問攻めにあっていた。
「いつ使えるのかわからない古いものを残しておく余裕は無くて。今、月では全てこの通信プロトコルに切り替えた。これなら宇宙嵐の影響を受けず通信できる」
瞬時に月からの映像が届けられる。その通信速度にどよめきが湧き起こった。
その人だかりへゴワゴワの宇宙服を身にまとった人間が全速力で近づいて来る。人々は恐々として道を開けた。
そして、その勢いのままシンセに飛び蹴りを食らわせた。シンセは吹き飛ばされて地面をゴロゴロと転がった。周りが一斉に道を開けた。
「あんた、もうちょっとでぶつかるところだったじゃないの!!」
目を血走らせたミライはシンセの胸倉をつかんで、吠えた。
「あっ姉ちゃん?」
「あっ姉ちゃんじゃないわよ。あんたね、どれだけの人に迷惑かけたと・・・」
ミライはシンセに向かい合って、ふと気付く。
あれ?こんなに大きかったっけ?小さかったのに。背を抜かされてる。
「ごめんごめん。本当はもうちょっと手前で着水する予定だったんだ。宇宙嵐の影響がまだ残って・・・」
次の瞬間、シンセは正面から両腕で締め付けられた。
宇宙服の厚みもあった。本当に呼吸を止められそうな力だった。シンセはミライを引き離そうとするが、引き離せない。
「く、苦しいよ、姉さん」
「もう心配させないで・・・」
嗚咽する姉の姿を見て、シンセは抵抗するのを止めた。
「地球はいいね。空気がうまい」
シンセは、胸一杯に空気を吸い込んだ。
数日のうちにシンセの持ち込んだ通信機器により月との交信が回復した。互いに港の機能は失われておらず、来週早々には定期便が再開されることが決まった。
一方、拘束されていたシンセの検疫が終わり、自由の身となった。しかしながら行く当てのないシンセはミライのマンションに転がり込むことになった。
「これこれ、懐かしい。月は肉が貴重なんだよね」
シンセは姉のシチューに貪りついた。
「そんなに慌てて食べなくてもいっぱい作ってるから」
ミライは弟の口元についたシチューを拭いてやった。
そんな二人の姿をアシタが見て、
「ホント、おまえら昔から仲いいよな」
とぼやく。アシタはミライの幼馴染で、昔からよくここに遊びに来ていた。弟の面倒を見る姉の姿を覚えている。
「そんなことより、二人はまだ結婚していないの?一緒に暮らしているんでしょ?」
シンセの問いかけに二人は顔を見合わせる。
「おれら、もう10年以上の付き合いになるしな」
「そうそう。なんかもう今更って感じだよね」
アシタは一呼吸を置いた後、
「そうだな、子供でも出来たら考える」
アシタの言葉にミライは顔を赤くして目を逸らした。
「ふーん。言うの忘れてたんだけど。おれ結婚してもう子供もいるから」
ミライは手にしていたスプーンを落とした。床にシチューがこぼれた。
「いつ?」
「2年前」
シンセは話を続ける。
「月が一番大変だった時期だったんだ。エネルギーが尽きかけてみんな生きるのに必死だった。死んだ仲間もいる。その時、彼女が色々と助けてくれたんだ」
空気も水も無い月での生活は想像するのに難しくない。まして生命線であるエネルギーが無くなれば命に関わる。
「それにおれももう22歳だからね」
シンセはおかわりの皿を差し出す。その皿を受け取り、
「ねぇ、子どもは何て名前?」
とミライが尋ねた。
「イツカ。いつか宇宙嵐が終わって、いつか地球に3人で行こうって。月で初めて生まれた赤ん坊なんだ」
「いい名前だね。今度帰ってくるときは3人で来なよ」
「うん」
シンセはうなずく。
「これ、アシタさんの?」
壁につるしてあった法被を指差す。緑色で背中に赤い文字で大きく地区の名前が入っている。
「そう。明日からお祭りだからな。おれはよそ者だからこういうときに参加しとかないと地域に馴染めない」
とアシタは付け加えた。
「そっか、もうこんな季節か。月には季節がないから気付かなかった」
ミライはシンセにシチューのおかわりの皿を差し出しながら、
「お祭りやりたいんなら、あんたの法被も捨ててないからまだどっかにあると思うよ。出そうか?」
「ほんと?」
その言葉にシンセは子供のように目を輝かせた。

お祭りの日は厚い雲に覆われていた。天気予報はどっちつかずの50%。今にも雨が降り出しそうだった。
秋になるとこの地域では豊穣を祝して各地区で神輿を出す。かき棒に大人が20人も群がれば一杯になるほど小さな神輿だったが、それが10台ほど集い、各地区の神社を廻る。
神輿のかき棒を肩で支えて老若男女が闊歩していた。同じ法被を着てシンセ、アシタがその輪の中に加わる。
太鼓と鐘に合わせて発せられるかき夫の掛け声は変わらず、神輿のかき棒の重みがシンセの記憶を思い出させた。他のかき夫同様に声を張り上げてみた。普段、こんなに声を出す機会はない。
アシタも負けじと声を出した。
「あれ?何かかき夫、少なくない?」
記憶は曖昧だが、前はもっと肩が触れ合うほど密集していたように思うし、順番待ちをするほど神輿の周りにも人が溢れていたのに、今はかき棒が密にならないほどにスカスカに空いていた。
周りの音にかき消されないようにアシタはシンセに耳を寄せて、
「月に比べたら地球の方がまだマシだったと思うけど、地球(こっち)もそれなりに大変だったんだ。実はお祭りも3年ぶりなんだよ。この3年のブランクは大きいよ」
神輿は神事のため、身内が死去した場合は汚れると言われ、触ることができない。シンセは納得した。
神輿は稲刈りの終わったあぜ道を進んでいく。シンセもアシタも汗だぐになりながら神輿を担いだ。
「やっぱお祭りって楽しいね」
シンセの言葉にアシタは理解できないと首を傾げた。
「おれはここの人間じゃないから楽しそうなふりはできても本当はどう楽しんでいいか、解ってないんだ」
「なーんも考えなくていいよ。楽しんだもの勝ちなんだから」
シンセは掛け声をラップ調にアレンジして叫んだ。周りの一同は白い目で若者を見つめた。
「お祭り、どうだった?」
ベランダから洗濯物を干しながらミライがシンセに呼びかけた。
「すげー面白かったよ。お祭りがあったらいいよね。月に戻ったらお祭り作ろうかな。そうだ、月まつりにしよう」
「何それ。そのネーミングセンス、無いわ」
「別に名前じゃないから。お祭りがあったらいつでもは帰れなくてもその時は帰ってきていいっていう合図なんだよ」
「それに堂々と仕事を休める言い訳になるだろ」
「そうかな。この地域だけのお祭りだから。遠方の人にはその言い訳は通じないよ」
お祭りは夜になっても続いていたが、途中でお腹が空いてミライは一度帰って来た。この地域のお祭りは明日の朝まで夜通し続く。
シンセはお湯を沸かしてカップラーメンに注いで、間髪入れずにすぐ食べ始めた。カップラーメンをすすりながらベランダに出る。
姉の口元は赤い光がホタルのように灯っていた。以前はタバコなんて吸っていなかったのに・・・。美味そうに白い煙を吐き出す。
「また月に戻るの?」
「うん」
「また宇宙嵐がいつ起こるのかもしれないのに?3人で地球暮らせばいいじゃない」
シンセはカップラーメンの汁を最後まで飲み干す。
「それでも戻るよ。だって、あそこに帰れる場所作らなきゃ。それがおれの仕事だから」
「そっか。あんたたちは人類の希望なんだから頑張っておいで」
「あ、それ。前にも同じこと言われた」
「そうだっけ?」
姉は短くなったタバコを灰皿の淵で揉み消す。
夜風が涼しくて気持ちよかった。その夜風に乗って遠く神輿の太鼓と鐘の音が聞こえてくる。
(完)

