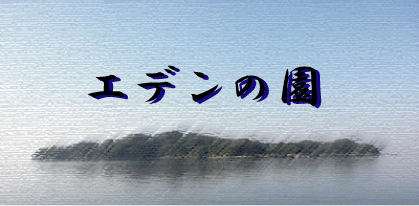
|
「ちょっと見て。今、魚が跳ねなかった?ほらあそこ」 「マジで?どこ?どこ。それってトビウオじゃね?」 若々しいカップルの二人だけが喧騒を作り出していた。男の方は光が透けそうなほどキラキラとした金髪で、女の方はもう少しで下着が見えそうなほど短いスカートを履いていた。 「ホントに宝物なんてあるの?」 「あるさ。見つかったら会社辞めて世界一周の旅に行こうぜ。まずはその前に祝杯だな。好きなものを好きなだけ食わせてやるぞ」 目の前の若いカップルの会話が狭い客室に響く。島と本土を結ぶ定期船には椅子に座り切れないほどの客を乗せていた。井瀬将太はうんざりしていた。このお祭り騒ぎが始まった一月前ならガラガラの船内にゆったりと座れていた。 瀬戸内に浮かぶ大庄島は、全周4kmに満たない小さな島だった。コンビニもなければ信号機もない。島には一軒だけ必要最低限の日用品を揃えた店と、あとは待合室に自動販売機が2台あるだけだった。現在87人の島民が暮らしている。その大多数を65歳以上の年寄りが占める。約二時間ごとに島を往復する定期船が島と本土を結ぶ唯一の交通手段だった。島へは30分ほどの時間で到着する。普段は往復5便が今は臨時的に7便にまで増便されていた。 島に小学校はない。校舎は現存するが、ずいぶん前に閉校になってから集会場代わりに島民がたまに集まるくらいで学校として機能していない。島で唯一の小学生の将太は本土にある近くの小学校に船で通学していた。 こんなことになったのは島で古銭が見つかったことがきっかけだった。昔からこの地域一帯には海賊がいたという伝説が残っていた。それに埋蔵金が眠っているとマスコミが騒ぎ立てて、一気に火がついた。それから全国から人が押し寄せてくるようになった。そういう輩は皆、本土の船着場で売られている地図を手にしているので判りやすい。地図には現在の島の地図と、裏面には宝の在りかを示すようなそれっぽい古い地図が印刷されている。 定期船が島に着くと、一斉に人や車が下船を始める。 港では宮原太樹が手を振っていた。その隣には新堂司沙の姿もあった。二人とも中学3年生になる。小学校が無いこの島にはもちろん中学校も無い。 「将太。今日は、キスだぞ」 その声で何人かの乗客が振り返った。皆、船着場で買った地図を手にしている。そういう約束を太樹と交わしていた。昨日がチヌの子供のチヌゴで、一昨日がヘビのような体のアナゴだった。キスは白い体をした魚の名前だった。今週は釣りを教えてもらっている。 将太は一度ランドセルを自分の家に放り込むとすぐ出かけた。港には漁師の父親の船が停まっていたが、まだ家には帰ってきていなかった。いつものように本土のパチンコ屋に行っているのかもしれない。 魚釣りの基本はエサ取りからだと、まずは海岸までやってきた。島ではヘムシと呼ばれる岩の裏にいる小さな虫をエサに使う。それは太ったミミズのようだった。 「ボク、何が取れんの?」 近づいて覗き込むのは先ほど船の中で遭遇したカップルの女性だった。男性の方は石を持ち上げて宝を探しているようだ。 女性にヘムシを見せてやると、ギャーと大きな悲鳴をあげて遠くに逃げて行った。男が待ってくれとそれを追いかけていく。島に来た人は宝を探して島中をあちこち歩いて、そのうち飽きて諦めて帰っていくのが常だった。 ヘムシを何十匹か捕まえると、それを持って移動した。チヌはチヌ、アナゴはアナゴ、キスはキスのいる場所がある。それは一部の島の人しか知らない。 大庄島は凹の字を逆さまにしたような形をしている。ちょうど窪みのところに港があり民家が集中している。道路は海岸線に沿って島を一周できるように一応は整備されているが、それ以外の大部分は森に覆われていた。島の住人は斜面にできた僅かな土地を耕し野菜を育てていた。ダイコン、ニンジン、ジャガイモ、キャベツ、タマネギの植えられた畑の脇を抜け、太樹の案内で港からまっすぐに山を越えて真裏の海岸までやってきた。 教えられながら仕掛けを調整した。錘はよく飛ぶようにといつもより重めにした。ヘムシの腹の辺りを釣り針で刺すと、中から緑色の体液があふれてきた。それを力いっぱい海へと投げ込む。投げ方も先週に教えてもらっていた。ポチャンと小さな飛沫があがった。あとは竿を前から後方にゆっくり引いて、竿を前に戻しながらリールをゆっくり巻いてを繰り返す。目当ての魚を誘う。 「キスの当たりは小さいから焦るなよ。じっくり食わせてから一気に引くんだ」 当たりとは魚がエサに食べに来る感触。リールを巻くと竿を通して錘が地面を這う感触がわかる。それが石ころに引っ掛かる感触なのか、当たりの感触なのか、わかりにくい。前者の感触を頭の中で消して、違うところがないか探る。何度かエサだけを取られた。その間、司沙は少し離れた岩に座って何かの書物をずっと読んでいた。 「今だ」 太樹の合図で将太は一気に竿を引いた。今まで手応えのなかった竿が一変して重くなる。魚が逃れようと暴れる感触が伝わってくる。リールを一気に巻きあげると、手のひらほどのキスがぴちぴちと跳ねた。 その後も何回か当たりがあって続けざまにキスが釣れた。そのうち小さなキスは海に逃がしてやったが、それでも6匹ほどバケツに残っていた。 「けっこう釣れたね。ここからは私の出番」 司沙が待ちかねたようにポケットから小ぶりのナイフを取り出す。エラの下に刃を当てて頭を落とす。鱗を取って内臓を取り出して、腹から背にかけてナイフを入れてあっという間に三枚におろした。 「はい、将太。自分でやってみて」 ナイフを手渡され、見様見真似でキスを捌く。手のひらの中で最後の抵抗を必死に暴れるキスは、目を見開いたままの頭を落とすと大人しくなった。それでもぬるぬるとした表面がつかみにくい。硬くて刃が思うように体に入っていかない。司沙に比べると出来は雲泥の差だった。それでも何匹か続けて捌いているうちにコツはつかめてきた。 その間に、太樹が薪を集めて火を起こしていた。ベラの身を炙ると磯の香りが一層強まった。きゅっと身が引き締まり皮に焦げ目が付いたところで、将太が食べてみると、塩と白身の加減がちょうど程良く口一杯に広がった。将太は釣ったキスを全部平らげた。 「どうだ?うまいだろ。あとは応用だからつりは今日で終わり。次は、銛の使い方を教えてやるよ」 将太は太樹から今月になって、サザエの取れる秘密の場所、島の中腹にあるアケビの取れる場所を教わっていた。 「ぼく、泳ぎはお父さんに教わって結構得意。島から本土までだって泳げる自信あるよ」 「バーカ。そういう油断が一番ダメだ。海は怖いんだぞ」 将太は、また明日と言って手を振って家路についた。海辺には太樹と司沙が取り残されていた。島の海に夕陽が沈み、海を真っ赤な色に染めていく。 「もう時間があんまりないよ」 「そんなことわかってる。だから早くやんなきゃダメなんだ」 司沙の影が細長く伸びていくにつれて、太樹の体は徐々に夜の帳に溶けていった。 太樹が目の前に現れたのは、司沙が学校に行かなくなって三日目の朝だった。このところ本土に働きに出ている司沙の母親は残業が続いていてこのところ帰りが遅い。おそらく学校に行っていないことにも気付いていないだろう。 目覚めると、すぐそばに太樹は立っていて、 「太樹なの?」 司沙の問いかけにただ黙って頷いた。 太樹が死んだと連絡が入った時、司沙は船に乗る直前だった。中学校の生徒会活動の打ち合わせで帰りが遅くなってしまった。暗い海の中を苛立つほど船がゆっくりと進む。船を下りると太樹の家へ全力で駆けた。太樹の家には島の人たちが集まっていて、只事では無い雰囲気が辺りに漂っていた。家に入るとき誰かに呼び止められたが、司沙の耳には一切入らなかった。一歩踏み出すごとに胸が張り裂けそうなほどに鼓動が高鳴っていく。 奥の部屋には、太樹のお父さんが座っていて、その前に横たわっているのは、紛れもなく太樹だった。まるで寝ているみたいに、いつもみたいに「よっ」って気安く話しかけてくるのを司沙はしばらく待った。いつもみたいに「宿題見せてくれよ」と泣きついてくるのを待った。しかしいつまで経っても太樹はそこに横たわったままでぴくりともしない。いつのまにか涙が溢れ落ちてスカートに幾つもの染みを作った。 だから突然、目の前に太樹が現れたときには全てが悪い夢だったんじゃないかと一瞬思った。 「司沙、悪い。おれ死んじゃったみたいだ」 しかし現実は現実のまま変わらない。それを聞いて涙が堪え切れなかった。 司沙が泣き止むのを待ってから、太樹は話し始めた。どうしてこんなことになったのか。死んでからどうしていたのか。 どうやら大人には太樹の姿は見えないらしい。触ろうとしても体は通り抜けてしまう。壁も床も自由にすり抜けられるが、望めば物に触ることも動かすこともできる。 それから島で唯一の小学生の将太に、魚の取り方や島の遊びを教えたいと太樹は言った。それらを教えないままに自分の世代で途絶えてしまうのは死んでも死に切れなかったらしい。言われてみれば司沙自身も、高校生になり島から出て行ってしまった2つ上の先輩から色々なことを教わっていた。 以来、将太と毎日会っている。確かに太樹と一緒に島を歩いていても将太以外は太樹には誰も気付かなかった。たまに島外からやってきた子供の視線を感じることはあるが、誰も太樹が死んでいるとは思わないだろう。司沙は自分がそのギリギリの境界線にいる。まだ将太にははっきりと太樹の姿が見えるらしいが、日に僅かずつだが太樹の姿が薄くなっている。 太樹の父親が、大庄島での水産加工の事業に失敗した。工場が閉鎖されてからガラの悪い借金取りが取り立ててくるようになるまで、そう時間は掛からなかった。それはまともに働いて返せる金額ではなかった。 「すまん、太樹。今日から本土に行くことになった。おまえはどうする?高校のこともあるから一緒に父さんと行くか」 島には働き口がない。本土に行けば仕事は紹介してもらえる。ただし決して楽な仕事ではないことは太樹にもわかった。 そのとき、太樹の頭に島の埋蔵金のことが頭によぎった。というよりも中学生の太樹にはそれしか思い付かなかった。 何年か前にこの島の沖で古い船が沈んでいるところを偶然見つけた。おそらく島民の誰も知らない。深くて潮の流れも速い場所だった。ずっと気にはなっていたが、まだ小学生だった太樹にはそこまで潜って辿り着ける自信は無かった。あれから体力もつき、泳ぎだって格段に上手くなっている。 少しでも潜る負担を減らそうと、大潮のときを見計らって太樹は海に出た。それでも5m以上は潜らないと辿り着けない。足ヒレをつけて潜れるギリギリというところだった。 ちょうど横穴に入り込んでいて海上からは見えない場所に船は沈んでいた。ここまで深く潜ると海の中は暗く冷たかった。持ってきた水中用のライトを照らす。船は木でできているが、腐らずにその原形を留めていた。全長10m以上はあるだろうか。 何度か繰り返し周りを探索すると船尾の甲板に入り口らしき階段を見つけた。次に息継ぎした後、中に入ってみる決意を太樹は固めた。 船の中に入ってみると、中は船首に向かって真っ直ぐに通路が伸びている。通路の左右の部屋があった。一番手前の部屋に入ってみると中には、大量のロープが置かれていた。部屋を一つ一つ見ている時間は無い。一気に奥まで行ってみる。突き当たるとさらに下に伸びる階段があった。一度戻ろうか、迷いながら中を覗き込むとそこは広い空間になっていた。どうやら船底らしい。そこでキラリとライトに反射するものを見つけた。それは錆びているが真ん中に穴が開いてある古いお金のようだった。 太樹が外に戻ろうとした時だった。船体が大きく揺れた。今まで静だった船内に潮が流れ込んでくる。押し戻され思うように前に進めない。やばい。息苦しい。必死に壁にしがみついて何とか船外に出た。 海面まであと少しだった。それなのにもう体が動かない。薄れゆく意識の中で太樹は父のことを思い出していた。 太樹の遺体は、島の海岸で発見された。その手には古銭を握り締めていた。中学生の不幸な事故はすぐに世間から忘れられ、後には埋蔵金の話だけが残った。 最期に教えるのは島に南西にある絶壁の上からの飛び込みだと決めていた。4m以上、3階建ての高さくらいある。島の子供なら皆ここから飛び込むのを儀式として中学校にあがる。まだ小学生の将太には早かったが、 「来いー、将太」 先に飛び込んだ太樹が叫んだ。地面を蹴って将太は跳んだ。躊躇は無かった。放物線を描いてドボンと水飛沫をあげた。
「おれにこれで教えられることは無いな」 将太が帰った後で、太樹は砂浜に寝転がった。太樹の体をカニがすり抜けていく。司沙には太樹の体がほとんど見えなくなっていた。その隣に司沙は腰掛けた。 太樹の父親には、島民がもしものときに入っている保険金と、島民が業者と話し合って宝の地図の売上の一部が入ることになっていた。それで借金はどうにかなりそうだと司沙は母から聞いていた。それでも息子を亡くしたショックで家に引き篭もったままだった。 「ねえ、他にないの?私には何にも無いの?」 「何にも無い。おまえは女だし。それに知っているだろ。おれが勉強できないことくらい。おまえに教えられることはあっても教えられることは無い」 きっぱりと太樹は言った。 「あっそうだ。埋蔵金の眠っている場所教えてやろうか?」 「そんなのいい」 今度は司沙がきっぱりと言い返した。 司沙は太樹の上に重なって寝転んでみた。太樹の透明な体をすり抜けて肌に感じるのは固い砂の感触だけ。あまりに距離が近過ぎると、ピントが合っていないみたいに太樹の姿は周りの景色に溶け込んでしまう。 「おまえはこれから、どうするんだ?」 「まだわからない。とりあえず島を出て高校に行って大学に行って、できれば島に戻ってきたい」 「そっか。それはいいな」 この島には働き口がない。島に残って暮らしている女性は、みんな漁師の嫁だった。 「だったらちゃんと学校行けよ」 「うん……、明日は行くつもり」 「ちゃんと好きなやつ見つけろよ」 「うんうん、あんたよりずっといいやつ見つけるんだから」 「ちゃんとご飯食べろよ」 返事しようとして声が詰まった。これ以上は耐えられない。司沙の瞳から堪え切れずに涙が零れた。 「ちゃんと歯を磨けよ」 「うん……」 「ちゃんと……しろ……よ」 太樹の声は段々とか細く小さくなっていき、やがて司沙には何にも聞こえなくなっていた。 (fin) |
