その日は朝から妙だった。
いつもなら一人で朝起きられないこの家の娘を起こすところからこの家の朝が始まる。今日はそのいつもより1時間以上早かった。
「なんでちゃんと前の日にちゃんと準備してないの!!」
母親の怒号が家の中に響く。
「あれどこ?」「これ要るの?」などと言い合いながら、母親と娘が家の中を駆け回る。まるで嵐のようだった。耳を塞ぎたくなるほどバタバタと騒がしい。
オレごと丸っと入れそうなもっと大きなバッグにゴーゴーと風の出る機械やひらひらする服を詰め込んで、
「じゃあ行ってくるね。バイバイ」
とコロコロと引いて出て行った。
「何がバイバイよ。もう帰ってくるんな」
そんないつもとは違う慌ただしさから解放され、母親が大きなため息を付いた。
今頃になって父親が起きてきた。こちらはいつもと変わらない朝。オレを見つけて頭を撫でてくる。シャーと思わず毛が逆立ちそうになるのを堪えた。
それなりに長生きしていると人間のことがそれなりに分かってくる。役所に勤めている父親と、パートに出ている母親、先ほど出て行った高校生の娘、それにこの家猫のオレ。その3人と1匹でこの家で暮らしている。
「いってきます。今日も留守番頼んだわね」
そう言って母親も出て行った。誰もいなくなった家にカチャリと音が響いた。
この家の留守番とはいえ、出来ることと言えばニャーニャーと鳴くことだけだが。
差し込んでくる陽だまりの中にオレは身体を丸めた。
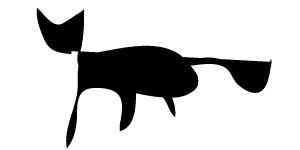
カチャリと音がして母親がパートから帰ってきた。
「ただいま。ごめんね、ひとりにして」
オレは家の留守番の任から解放されて背中を伸ばした。
そのうち父親が帰ってきた。オレはまた頭を撫でられた。
もう外が真っ暗だというのに娘が帰ってこない。今さらになってピンときた。以前にもこんなことがあった。
修学旅行。普段とは違う遠方に出向いて見識や見分を深めるらしい。それに親離れの訓練のひとつ。さぞ見聞を広めて成長して帰ってくるがいい。それにしても生まれて数カ月で引き離されるオレたちと違って人間はのんびりとしている。
食事が終わり、テレビの音が部屋に響いていた。どうやったらこの薄っぺらい箱の中から画像や音が出てくるのかよくわからないが、オレはこのテレビというやつが好きだ。家の中にいても家の外の情報が分かる。
今は食べ物をひたすら食べる番組を見ている。太った中年が口いっぱいにカレーライスを頬張る。しかも辛いらしく水をかぶ飲みしている。人間はこんなことをして何が楽しいのだろう。さっぱり分からない・・・。
「こんなにのんびりできるのは久しぶりだわ」
それを見て大笑いする母親がテレビを見ながらプシューと音の鳴る飲み物を開けた。
平和な朝だった。
その理由ははっきりしていた。いつも騒がしい元凶となる娘がこの家にいないから。
「こんなにのんびりできる朝は久しぶり」
と母親は鼻歌交じりに朝食の支度を整えた。部屋には焼いたパンの香ばしい匂いが漂っていた。
仕事に出ていく父親がオレの体を撫でる。本音を言えば気安く身体を触られたくはないのだが。オレは家猫の鏡だな。
「ごめんね。今日は遅くなるのよ。パパも飲み会で、私も久しぶりに友達と会うから」
そう言って機嫌良さげな母親もパートに出かけた。
ふと見るとエサ箱にはご飯が1.5倍のてんこ盛りになっていた。まあ別に遅くなったところで特に困ることもないが。
まぁ、誰しも息抜きも必要だ。オレは大きなあくびをして今日も留守番の任に就く。

オレは夢を見た。この家にやってきた頃の夢だった。
何がどうなってそうなったのか、わからないが、道端でボロボロの段ボールに入ってオレは泣いていた。当然、自分の母親の記憶もまだない。追い打ちをかけるように空からは大粒の雨が降り注いで体を濡らした。
誰か助けて。お腹空いたよ。寒いよ。
ふいに誰かの手に抱かれた。小さな手だった。温かい手だった。それがこの家の娘だった。まだその頃、娘は小学生だった。
それから寝る時はいつも娘と一緒だった。小さな体でお互いの温もりを感じた。オレと離れたくないからと小学校の修学旅行に行きたくないと泣いたこともある。
オレもその間に年月を重ねてすっかり大人になった。もう一緒に寝ることはなくなった。娘も高校生になり順調にいけば来年には大学生になる。こんな田舎から通える大学はない。遅かれ早かれ娘はこの家から出ていくことになるのだ。
「ただいま。飲みすぎちゃった」
バタバタと騒がしい母親の帰宅でオレは夢から覚めた。
静かな朝だった。
母親が弁当を作るトントンとまな板を叩く包丁の音、父親がめくる新聞の紙がすれる音が聞こえる。
朝食を食べ終えた父親がオレの頭を撫でて、仕事に出かけた。
そろそろ母親も出ていく時間のはずなのだが、なかなか洗面所から出て来ない。オレたちでいうところの毛づくろいでもしているのだろうか。人間の女性は特に時間がかかるのは知っている。それにしても遅い。
洗面所に行くと、母親が膝を抱えてその場にうずくまっていた。
どうした?お腹でも痛いのか。
オレは母親の手の甲をペロペロと舐めた。それでどうなるものでもないが、それでも舐め続けた。
すると母親は顔を上げて急に立ち上がった。
「ごめんごめん。じゃあ今日も留守番。お願いね」
母親は何事もなかったように家を出て行った。
あ、オレの朝ご飯、忘れられてる・・・。
母親がパートから帰ってきた。
やはり何か様子がおかしい。何も言わずに娘の部屋の前に立ち止まる。母親の足にすり寄ってみてもしばらくそこから動かなかった。ニャーニャーと鳴いてみたが、反応はない。
娘がいなくて寂しいのだろう。それが母親とはそういう生き物なのか。親にとっても子離れの訓練のひとつ。家族で一緒に暮らす方が珍しい猫にとって、別れはそう特別なことじゃないというのに。
オレは思う。こういうときこそ父親の出番なのでは、と。
仕事から帰ってきたばかりの父親にすり寄っていく。
「なんだ、おまえ遊んで欲しいのか?」
違う。そうじゃない。
オレは父親の手の袖を加えて母親の方へと促そうとした。しかし体格が違い過ぎてびくともしない。
「甘えてるのか。よしよし、撫でてやろう」
だから違う。お前の目は節穴か。いつもと様子が違うだろ。母親の方を見ろって。
その時、父親が放屁した。
く、くさい。鼻がまがりそうだ。
オレはイラっとして、頭を撫でようとする父親の手のひらに思い切り噛み付いてやった。

不思議な朝だった。
母親が朝食の支度をしていた。何か空気が違うというか。この違和感を猫のオレには何と表現すればよいのかわからないのだが。
天気予報による例年よりも5度以上気温が高いらしい。20年ぶりに行方不明になっていた仏像が見つかったとか。とある川にアザラシが姿を見せたとか。
父親がオレの頭を撫でて、仕事に出かけていく。
母親はまだ台所にいた。鶏肉を刻んで鍋の中に放り込んだ。中火でコトコトと煮込む。既に朝ご飯は終わっている。昼食を用意するにもこんなに時間がかかることはない。となると・・・、
「朝ごはんがまだだったわね。もうちょっと待ってね」
母親が言った。
オレの朝ご飯は、特別な日にしか出て来ない美味しいやつだった。
その日は珍しく、留守番中にピンポンが2度も鳴った。
とはいえ「うちに何か」とカギを開けてオレに応対できるはずもなく見守るしかなかった。しばらくすると帰っていく気配がした。同じ人間だったのか何の用事だったのか、分からないまま。
そうこうしているうちに「ただいま」と、母親が大きな買い物を抱えて帰ってきた。いつもなら「疲れた~」とゴロっとソファーに寝転ぶのにすぐに夕食の準備に取り掛かった。
母親は油を加熱して衣を付けた豚肉を揚げ始めた。部屋中に美味しそうな匂いが立ち込める。他にも生の魚の匂いもした。
母親は夕食を作りながら、何度も窓から家の外を気にしていた。
太陽が沈みかけて空を朱色に染めていく。今さらになってピンと来た。以前にもこんなことがあった。
遠くから聞き覚えのある足音が近づいてきた。もう何百何千回と聞いた足音だった。間違いない。
ゴロゴロとバッグを引きずりながら、ドアがガチャリと開き、
「ただいま。疲れた~」
この家の娘が帰ってきた。玄関に倒れ込む。そしてそのまま動かなくなった。
何かあったのか?怪我でもしているか?大丈夫なのか?
オレはオロオロと娘の周りを右往左往した。
「どうせ寝ずに友達と遊んでたんでしょ。あんた、そんなところで寝るんじゃないよ。洗濯ものがあったら出しなさい。臭くなるから」
母親が声を荒らげた。
「もううるさいな。こっちは疲れてっていうのに」
娘はむくっと起き上がる。
「ただいま。会いたかったよ~」
オレは娘に抱きすくめられた。
それから父親が帰ってきた。返ってくるなりオレの頭をひとつ撫でた。
テーブルに並んだご馳走を前にして、テレビの音に負けないくらいの音量で娘が修学旅行での出来事を語る。
やれやれ。まだしばらく騒がしい日が続きそうだ。
(完)

