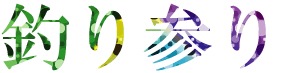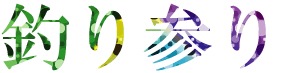「おとな1名。と、お嬢さんは何年生?中学生?」
少女が答えないでいると「すみません。中学生です」と代わりに中年男性が答え、代金を支払った。
「失礼しちゃう。どこからどう見たって中学生でしょ」
少女は口を尖らせた。
「君は大人っぽいから高校生くらいに見えたんじゃない?」
そっぽを向いたまま、やはり少女は何も答えない。
島へと向かう船は白波を立てて進んでいく。甲板は思っていたよりも風が強い。中年男性は被っていた帽子を飛ばされないように深く被り直した。
島に着くと、一斉に人々が降り始めた。思っていたよりも客が多いし、先客もいるようだった。いい場所を取られないように我々も急がなくては、中年男性は思った。
「トロトロしないで。遅いと置いてくから」
少女の後を慌てて中年男性が追いかけていく。
この島に来るのは一年ぶりだった。なるべく人が周りにいない防波堤を見つけて荷物を下ろした。毎年、中年男性と少女はこの島を訪れていた。釣りをするために。でもここでの普通の釣りとは少々違う。
普通なら魚が食べるエサを使うところだが、中年男性は持ってきたエサを取り出す。ペン、消しゴム、箸、フォーク、カエルのキーホルダー、カエルのぬいぐるみなどなど。申し訳なさを感じながらを針にそれを付ける。
少女も同様にカバンからイヤリングを取り出した。
「えーっ、それ高かったんだよ」
「いいじゃない。要は取られなきゃいいんでしょ」
「もう君は昔からそういうの怖れないよな」
少女は一連の作業を的確にこなして先に竿を振った。水面に波紋を立てた。リールを巻く姿も様になっている。
続けて中年男性も竿を振った。勢いよく弧を描き、小さな水しぶきをあげた。
この島では魚を釣るのにコツはある。どれだけ自然と一体になれるか。まずは波と一体になって気配を消す。そしてここからが一番大事なところ。目を閉じてイヤリングの思い出を念ずる。それは鮮明であればあるほど強ければ強いほどいい。
魚が突っついて来た。でもまだ警戒している。一気には来ない。もっと引き付けてから。まだ早い。もう少し・・・。
少女は竿を引いた。その途端、竿を通じて抗う感触が伝わってくる。リールを一気に巻くと白い魚影が浮かび上がってきた。
釣れたのはフグだった。少女がフグに触れた途端、頭の中に映像が流れてくる。
目の前に立つ女性には見覚えがあった。霞がかかったようにぼんやりとしてその表情までは見えない。
「ダメでしょ。これはもっと大人になってから」
私は頭を撫でられた。あの時は怒られたような気がしたのに。そして少女は幻影から覚めた。
このイヤリングはママが出かけるときによく付けていたものだった。小さな赤い宝石が付いてあって、大人になればいつか自分も付けたいなと思っていた。
「上手くなったね。初めて君に先に釣られた」
「バカにしてる?次はもっと大物を釣ってやるんだから」
少女は釣りあげたフグを海に戻した。
「えっ、逃す前にもぼくにも見せてほしかったのに」
釣った魚は他の人が触っても同じ幻影を見ることができる。なぜかはわからないが、この島ではそれが普通だった。この島では釣った魚は海に返す決まりになっている。そうすると幻影がリセットされる。持って帰ろうとしても帰りの船でチェックされて没収されてしまう。
少女はエサにつけていたイヤリングもちゃんと回収した。ごくたまに魚に取られてしまうこともある。エサは一回使うともう二度と魚は釣れなくなる。
「おっ、ぼくにも来たかな」
今度は中年男性にも当たりが来た。竿がつの字にしなる。リールを巻くのにも力が入る。釣れたのはイカだった。その10本の足でしっかりとカエルのぬいぐるみをとらえている。昔から彼女はカエルが好きでグッズを収集していた。これは出会う前から持っていたものだった。
中年男性がイカに触れるとぬめっとした感触があった。頭の中に映像が流れ込んでくる。
彼女は手のひらにアマガエルを捕まえて、こちらに迫ってくる。
「本物のカエルに触るの初めてって、それホント?」
彼女がそう言って笑った。思わず彼女の手に触れようとして、触れる直前でしゃぼんの泡のように消えてしまった。
見える幻影は、自らが体験した出来事であって経験してないことは出てこない。まして思い出には触ることなんてできない。
ほんの数秒だったけど懐かしくて心地いい、確かに彼女の声だった。
「そっちこそ、ぬいぐるみがびしょ濡れじゃない」
「帰ったらちゃんと洗って干すから、別にいいの。君も見る?」
「いいよ、自分で釣るから」
イカは逃がしてやると、スミを吐きながら海へ潜って見えなくなった。
中年男性は次にカスタネットをつけてみた。これは友人の結婚式の歌の余興で使ったやつだった。彼女がカスタネット、中年男性はトライアングルを担当した。本番は緊張して何度かミスってしまったけど、夜遅くまでみんなで練習したことを覚えている。
そんな思い出と一緒に、薄べったいカレイが釣れた。
次に香水をつけた。漏れないようにしっかりとフタを閉める。微かに彼女の匂いがした気がした。

「けっこう釣れたね、そろそろエサもなくなってきた」
中年男性の周りには使用済みのエサが山積みになっていた。
「こんな雑魚、何匹釣ったところで意味なくない?」
そういう少女の周りにも使用済みのエサで溢れ、残りのエサはわずかになっていた。釣ったそばから逃がしてやるので、手元には一匹も残ってはいないが。
「もっと大物を釣らなきゃ意味がない」
少女は指にはめていた指輪を外しては針につけた。
「あーっ。それはぼくが君にあげたやつ」
時すでに遅かった。中年男性の視線は投げられた指輪を追いかけるしかなかった。
「大物って君はクジラでも釣るつもりかい?」
大事なものであればあるほど思いが強いほど、大物が釣れる。大物であればあるほど、見える幻影が強くなるという。中には嘘か本当か、故人が帰って来たという逸話まで残っていた。
「ねぇ、指輪の思い出なんてあるの?」
「ない。全然覚えてない」
少女は表情一つ変えずに言う。
「ははは、それはそうだよね。そうしたら僕の出番だ」
中年男性は、少女の背後に回り釣竿を握りしめた。
「ちょ、ちょっと待って。これ、恥ずかしいやつじゃないでしょうね」
「な、なに言ってるんですか。そんなわけないでしょ」
竿が急に引っ張られた。
少女も中年男性も足を踏ん張り、ぐっと竿を握り締める。それでも相手が引く力の方が勝っていた。竿の先から海の中に伸びた糸が右へ左へと走る。
「何これ!?でかい。ほんとにクジラ?」
急に引く力が無くなった。糸が切られたか、針が外れちゃったかな。
次の瞬間、ものすごい力で引っ張られて少女と中年男性は海に落ちた。
少女は深い海へと潜っていくクジラの姿を見た。竿はまだ手の中にあった。ものすごい勢いでまだ引っ張られていく。まだ諦めるわけにはいかない。もらった指輪を取られてしまう。それにあれを捕まえたら本当に戻ってくるかもしれない。
でも少女の手を竿からほどいたのは中年男性だった。
「惜しかったね」
二人ともずぶ濡れだった。ぽたぽたと水滴が防波堤のコンクリートに模様をつけていく。
少女は持ってきていたタオルを取り出した。念のために着替えを持ってきておいてよかったと思った。
「ごめん、指輪失くした・・・」
「別にいいんだよ。指輪よりもっと大事なものを失くすところだった」
この島では取られたエサは必要のないものとして戻ってこないと言われている。もうぼくには必要ないのかなと中年男性は思った。エサとなる品々は年々少なくなるし、だんだんと良いものが減っていく。あんなにたくさんあったはずなのに。
この島の噂を聞いて初めて来た3年前、彼女の思い出の品を持ち出して泣きながら釣った。それはもう号泣といっていいほどだった。涙が枯れるまで釣りをした。
昨年は初めて少女を連れてきた。少女も中年男性と同じように泣いた。それなのに今年は二人とももう涙は出なかった。
帰りの船の中で少女と中年男性は並んで席に座ったが、会話はなかった。辺りはすっかり日が暮れて暗くなっていた。真っ暗な海を灯りに引き寄せられかのように船は進んでいく。
そしてもと来た港へたどり着いた。船から降りると、
「また来年」
それだけ言うと少女と中年男性は別れた。それぞれが帰る場所へと歩いていく。振り返らず真っすぐに。
(完)