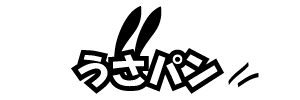
|
カレは変わっている。 腕と足と胴まわり、それに耳と目のまわりが黒い。それがワタシたちパンダの特ちょうだ。同じパンダのくせに、なぜか黒い耳だけはぴんと伸びてウサギのように長い。人間たちはカレのことを「うさパン」と呼ぶ。 「きゃー、うさパン。こっち向いて」 今日も黄色い声援が飛び交う。同じ動物園にワタシという同じパンダがいるというのに、カレの人気はとびぬけている。というのも、カレは先日行われた「全国動物人気グランプリ」で、昨年一位だった2本足で人間のように立って歩くシロクマや、寒がりのハラまき姿で有名になったペンギンをおさえて、人気一位を勝ち取った。元々の人気に加えて、全国からカレを目当てにお客さんが押しかけてくるようになった。休日になるとカレのオリの前には行列ができる。 カレはおしりをボリボリとかきながら寝ていた。 カレはとにかく変わっている。 「来年が来たらこの動物園をやめてふるさとの山に帰る」といきなり宣言した。それをきいた園長は真っ青になって何度もカレを引き止めた。でもカレの決心は揺るがなかった。来年の春が来たらここを出て行くと、きっぱりと言った。 「ここに来るときから一位になったらやめようって、決めてたワン。ここにいたらいつも同じような毎日だろ、一生いてもつまんねえワン」 カレの中で言葉のあとに「ワン」をつけるのがはやっているらしい。その前はたしか「ニャン」だった。 一度、動物園に入った動物が自らやめてしまうのはめずらしいことだ。ここにいれば食べものにも困らないし、ほかの動物におそわれることもない。ワタシはパンダだからと、わりと簡単に入れてもらえたけれど、入りたくて入れない動物たちもたくさんいるときく。 それでも動物園にいれば一生安心というわけではない。経営が苦しくなれば食べものもコスト削減で減らされる。グランプリ10位以内にも入れないワタシは、今まで京都産の天然もののササだったのが、近所で取れる普通のササに変わったこともある。おいしくなくても文句は言えない。また人手が足りないときには園内のそうじだって手伝わされる。 「おまえたちにまでこんなことさせてすまんな」 園長は自らもそうじしながら、申しわけなさそうに言う。 でも人気一位になった動物は、決まって応援したいというスポンサーがついたりするので、そんな心配もなくなる。 動物園にいれば三色昼寝つき。お嫁さんだって、こちらが出向かなくても向こうの方からやってきて、選びほうだい。代わってほしいくらいだ。 「オレはそんなことに興味ないワン」 カレはおしりをボリボリとかきながらそう言った。 カレはやっぱり変わっている。 毎年の園内でいく旅行のバス移動で、カレのとなりの席になったことがある。今年は延長がふんぱつして伊豆にある温泉に行くことになっていた。 カレはカバンの中から食べものを取り出した。このとき、知ったのだが、カレは甘いものが大好きだ。ワタシもふくめて普通のパンダはササが好物だが、カレはイチゴやバナナのような果物でも、人間が作ったお菓子も食べる。飼育員の田中さんに作ってもらっているササ茶と合うらしい。でも自然に帰ればそんな生活もできなくなってしまうというのに。 「別に山にだって甘いものはあるワン。ササ茶はなければなければでがまんするワン。川の水を飲めれば別にいいワン」 カレにお願いしてカレの長くて黒い耳をさわらせてもらった。いったいどこまでが毛でどこまでが耳なのか、ずっと気になっていた。さわるとフワフワとしてやわらかかった。ワタシにもこの耳があれば人気者になれるだろうか。 「おれはこの耳のおかげでここまで人気者になれたワン。小さいころはこの耳のせいで仲間にもよくからかわれたワン。でもそのおかげで強くなれた。別におれになる必要なんてない。やっぱり動物は本能のままに生きるのが一番ワン」 カレはお菓子をバリバリと食べながら言った。 そしてついにカレが動物園を去る日がやってきた。 動物園ではカレのお別れセレモニーが行われることになった。これまでにないくらい人間たちがやってきてカレのオリを取り囲んだ。 「うさパン、いつかまた戻ってきてね」と若い女性がなごりおしそうに写真をとりながら言った。 「お願いだからやめないでくれ」とよく来る近所のお年寄りの男性が力いっぱいさけんだ。 「山に帰っても元気でね」と幼稚園の子供たちが泣いていた。 オリの中に作られた特設ステージの上にカレは立った。 「みなさん、きょうはおれのためにこんなに多くの人たちが集まってくれてどうもありがとう。でも今日でおれのことは忘れてくれ。この動物園にきてもオレはもういない」 カレは言葉を続ける。誰もがその言葉を黙って聞いていた。 「でも、この動物園にはまだまだすばらしいたくさんの動物たちがいる。おれの分、ほかの動物たちのことを愛してやってくれ」 カレに向けられた送られた拍手は人間だけでなく動物たちからも送られた。それは動物園中に響いていつまでも鳴り止まなかった。 ワタシは飼育員の田中さんに頼んで、作ってもらったササ茶を入れたペットボトルをカレに渡した。 「じゃあ、わしは行くでござる。おぬしも元気でな」 いつのまにか今度は「ござる」に変わっていた。それがカレとかわした最後の言葉になった。 それからしばらくの間、動物園は客が大きく減ってしまった。ワタシもだいぶそうじを手伝うことになった。でもしばらく過ぎるとまた元のように客が戻ってくるようになった。 カレが望んだように人間はだんだんと、カレのことを忘れていく。近頃はうさパンの話をきいたことがない。ワタシもいつかは忘れてしまうのだろうか。カレの耳のあのやわらかさを。 (完) |
